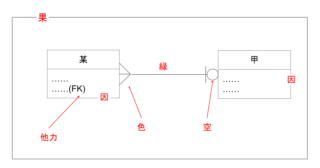引き続き60年前の古書、平凡社の世界教養全集第12巻、「美の本体(岸田劉生)/芸術に関する101章(アラン)/ロダンの言葉(A.ロダン)/ゴッホの手紙(V.ゴッホ)/回想のセザンヌ(E.ベルナール)/ベートーヴェンの生涯(ロマン・ロラン)」を読んでいる。
収載書の二つ目、「芸術に関する101章 Préliminaires à l’esthétique 」(アラン Alain 著・斎藤正二訳)を読み終わった。
原題は「美学入門 Préliminaires à l’esthétique 」であるが、訳者(斎藤正二)が原書の著述経緯から、訳書名を「芸術に関する101章」としたものだそうである。
著者のアランはフランスの哲学者で、日本で言えば明治時代に活躍した。本書は101の掌章からなる芸術論である。一つ一つの章は短いので、肩を凝らせずに読むことができる。内容も
本書でアランが一貫して説いているのは、芸術における
面白いのは、当時出現したばかりで、発展中であった「レコード」や「映画」や「ラジオ」について、決して受け入れようとせず、芸術としては最悪だ、というふうに
気になった箇所
他の<blockquote>タグ同じ。p.114より
しかるに現代は、つまらない発明にあふれ、このことが大衆の趣味を堕落させ、いっぽう、識者に非難の声をあげさせているわけだ。しかし、いつの時代でもこのとおりであった、と私は思う。気違いどもが発明している間に、賢者たちは、せっせと模倣していたのだ。模倣者のうちでも、いちばん生気のある者が、おのれの気質を、おのれの絵筆の癖を、おのれの
鑿 づかいの癖を、おのれの風刺を、おのれのアクセントを、そのなかに盛りこんだのであった。
崇高な
筆致 というものは、つねに、しごく平凡なものである。崇高な曲も同じである。多くの作者は、自力でそれを追求したかのような感をいだかしめる。しかも、ついにそれを発見しえた者は、他人の仕事からなにをえたかについては、けっして、語ることができない。ストラディヴァリウス(ここは、イタリアのクレモーナの楽器製造人アントニオ・ストラディヴァリウスをさしている。一六四四―一七三七年)は、新しいヴァイオリンの形を発明したのではない。ゴチックの大伽藍は、誰の発明によるものでもない。
模倣し、模倣しぬくべきなのである。そして、模倣しながら発明すべきなのである。模倣することによって飛躍をうる芸術上の独創の秘密は、じつは、ここに隠されているのだ。それは、音楽家が、巨匠の書いた曲を弾くことによって、みずからの飛躍をうるのと、ちょうど同じである。
ミケランジェロの彫った首一つを見ただけでも、もっとも驚嘆すべき独創というものが、きわめてありふれた事物に近いことを、悟らされるだろう。それは、まったく、凡庸と紙一重である。だが、才能のない職人と比べてみるならば、その差異は、はっきりしているのだ。
今日の芸術家たちが、目先の新しいものとか、前人未到のものとかを、躍起になって追い求めているさまを見ると、私は、ふきだしたくなるのである。
『第九交響曲』のいおうとすることを、一ページか二ページの散文でわからせることができると仮定したならば、もはや、『第九交響曲』は存在しないであろう。音楽が風の音や雨の音を模写するとき、その音楽は、時間を浪費しているのだ。音楽が悲劇的情熱を叙述するとき、その音楽は、時間を浪費しているのだ。一言でいえば、ある芸術作品が芸術作品たりうるのは、それが、おのれ自身しか表現していない場合である。すなわち、それの表現しているものが、他のどんな言語にも移しかえられないという場合である。
教養とは、最良のモデルを前にしての、絶えざる物真似であり、絶えざるサル真似である。
ひとを説得する技術は、けっして、聴く者の意見を変えることにあるのではなくて、かえって、これに、理性らしい外観をじょうずに与えることにある。
宮廷人であったゲーテは、
お化け をばかにしたが、そのことによって、ゲーテ自身もまた、お化けであった。しかし、ゲーテは「永遠なもの」をも見た。「あらゆる人間は、その立場において、永遠である」と、彼はいった。芸術とは、物事をけっしてばかにしない、こうした記憶をいうのである。ファウストは、それ自身によって、永遠に存在する。
だから、名将軍である以前に、まず、将軍であらねばならないのである。つまり、実際の敵軍を前にして、実際の軍隊を指揮しなければならないのである。
懐疑論者のなかでも、おそらくいちばんの変り者であるヒューム(デーヴィド・ヒューム。科学を信ぜず、ひたすら経験と観察とによって普遍的原理を探求しようとしたため、懐疑的実証主義と呼ばれる。1711-76年)は、直線が円と接することは不可能だということを、おもしろがって唱えたものである。――なんとなれば、この二つの線に共通な点が一つなければならない。ところで、円上のもっとも小さな点も、つねに円に属している。すなわち、曲がっているはずである。また、直線状のもっとも小さな点も、つねに直線である。ゆえに、この二つのものは、合致することができない。そう、ヒュームはいった。
上記のことは、無論、「接線とは何か」を考え抜くことによって微分法に到達したライプニッツと、「速度とは何か」を考え抜くことによって微分法に到達したニュートンによって、同時に整理されてしまっている。本書中でも、上の引用の直後の部分に「ライプニッツはそれをはるかに超越した次元からこの
私はミケランジェロの手紙を読んだ。あなたがたにも、一読をおすすめしたい。まるで、石工の仕事場にはいったような気がするだろう。このどえらい男が、一度も、美ということを念頭におかなかったのは、明らかである。彼は、一つの作品を手がけたかと思うと、すぐに、べつの作品へと移っていった。彼の心労の
種子 はといえば、大理石をどうやって手に入れるか、石切り職人や船頭や車引きに支払う金をどうやって手に入れるか、ということであった。彼は「すばらしい霊感がやってきてほしい」などとは、絶対にいわない。そのかわり、彼は「材料と時間とがほしい。新しい教皇が、前任者の計画を続けてくれればよいが、と思う」というのだ。長期にわたる、困難な仕事のことだけが問題なのであって、完璧な美しさに仕上げたいとか、感情を表現したいとかいったことは、どこにも書いていないのである。その語調は、あくせくと心を労し、気むずかしい主人を持ちつつ、稼業に精だして働く、辛抱強い男のそれである。自意識というものもなく、名声を欲する考えもない。私には、これほど、自分自身に対して身を潜めた、滅私の芸術家がいた、とは思われない。このような男にあっては天賦ということも、仕事がうまいという以外のものでは、絶対にありえなかったし、趣味の悪さということも腕の悪さにしかみえなかったのだ、とまでいいきることが必要であろう。バッハも、同じように、だめな音楽家のことを、「あいつは、自分の稼業に通じておらん」といったかもしれない。こうした見識は、天才に特有のものである。
「指揮をとってる最中には、
人間 などという名詞は、どこかへ吹っ飛んでしまう、などといったひとは、かつていたためしがありませんでした。ところが、僕の中隊長は、僕にそういったのです。僕は、彼の部下の一人でした。僕は、一人の人間にすぎなかった。人間か! という言葉。人間以上に侮蔑されたものが、他にあったでしょうか。人間以上に罵 倒 され、忘れられ、やすやすと消費されるものが、他にあったでしょうか。しかし、人間 という言葉は、響きがいい。それは、すべての位階の上にある位階です。僕は、人間の名にふさわしい値うちをもっているでしょうか。いずれにしても、僕は、人間であることを選んだのです。」
こうして、定型詩がもっとも美しいということ。定型詩のうちでも、韻が美しくさえあるならば、韻を踏んだ定型詩こそが、もっとも美しいということ。そのことを、私は理解するのである。
日本の定型詩である歌や句が美しいということに通ずるものがあり、むしろ逆に古風だな、とも感じた。
言葉
糧
普通に訓読すれば「かて」であるが、本書中で一箇所、「やしない」とルビを振って
しかし、「やしない」とはゆかしい言葉であって、違和感もなく、意味も字義も通っているように思う。
あらゆる武器に装飾がほどこされてあるということは、驚くべきことだ。このことは、おそらく、戦争に関するわれわれの思想が、やはり
糧 を求めているということを、りっぱに証 しだてている。
かなつんぼ
恥ずかしながら、この言葉を全く知らなかった。「ひどい聾」で、まったく聴こえないことをこう言うそうな。
- 金聾(かなつんぼ) の意味(goo辞書)
あまりにみごとすぎる言いかただね。それでは、
世界 は、人間のうちにあるあの非人間的な部分、機械のように話したり行動したりする部分ということになってしまう。そして、その部分は、物体がそうであるように、人間に対してはかなつんぼだということになる。
次
次は三つ目、「ロダンの言葉」(A.ロダン François-Auguste-René Rodin、高村光太郎訳、今泉篤男編)である。
オーギュスト・ロダンは言わずと知れた彫刻の巨匠である。日本にも作品はあり、上野の西洋美術館前にある同鋳の「地獄の門」や「考える人」、「カレーの市民」を知らぬ人はあるまい。